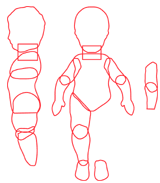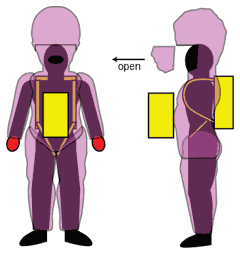|
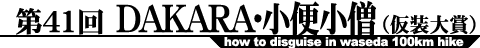 |
軟質ウレタン製ボディは、保温性抜群。
動きやすいけど、天気が良いと地獄を見る。

|
| 衣装データ |
| モデル |
DAKARAの小便小僧 |
| 形状分類 |
ハリボテ+着ぐるみ型 |
| 選択理由 |
当時のCMから |
| サイズ |
210×60×45cm |
| 装着時頭頂高 |
210cm |
| 重量 |
7kg |
| 外面材料 |
ニット・ラテックス塗り |
| フレーム材料 |
発泡スチロール
軟質ウレタン |
| その他の材料 |
布
モデリングペースト
ジエッソ |
| 雨対策 |
専用防水カバー |
| 歩き易さ |
普通 |
| 手の振り |
普通 |
| 通常視野 |
狭い |
| ハッチ開閉時視野 |
良好 |
| 後方確認 |
体ごと |
| ゴール |
20時 |
|
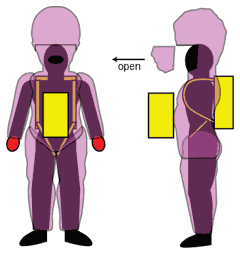
|
| 構造図 |
 |
肌に密着していない装着物とそのフレーム |
 |
肌に密着している仮装用装着物 |
 |
仮装に準じた形状に加工したバックパックや仮装固定具 |
 |
仮装に関係ない荷物やバックパック |
 |
仮装用装着物なし |
| ←open |
視野確保用ハッチ |
|
■説 明
記念すべき10回目の百ハイ参加の仮装は何がいいかなぁ?と考えた時に「本来は動きそうに無い物が動くと面白いのでは?」と思って目をつけたのが、前々から気になっていたDAKARAの小便小僧。
この小便小僧を作る際に、絶対に忘れてはならないは「放尿」機能…これを実現すべく、実際のDAKARAのペットボトルを改造して作った尿タンクを背中のバックパック内に収納し、片方のホースから息を吹き込むともう片方のホースからタンク内の尿がでるような仕組みになっています。
  ただ、タンクの位置が股間よりも高いためにサイフォンの原理により一度放尿が始まると、タンクが空になるまで放尿を続けてしまう「尿漏れ」が発生するので、放尿を止めるためには「息を吸う」という作業が必要になります…でもやはり、尿の切れが悪く、どうも年寄りっぽいパフォーマンスしか出来ませんでしたが(汗)
ただ、タンクの位置が股間よりも高いためにサイフォンの原理により一度放尿が始まると、タンクが空になるまで放尿を続けてしまう「尿漏れ」が発生するので、放尿を止めるためには「息を吸う」という作業が必要になります…でもやはり、尿の切れが悪く、どうも年寄りっぽいパフォーマンスしか出来ませんでしたが(汗)
構造上、すき間が少ない上に保温性が高く、動かなくても汗だく。当日は幸いにも曇り時々雨だったので地獄を見ずにすみましたが、それでも、裾から汗をボタボタ垂らしながら、道中4リットルほどDAKARAを消費しました。ゴール後に体重を計ってみたら、4kgほど痩せてましたし。
手に持っている大きな缶は荷物入れも兼ねているだけでなく、全体が反射材で出来ていて、夜歩く時の安全性も高めてくれる優れものです。歩行時は胸のハートの下にあるフックに引っ掛けられるようにしていました。
最後の休憩所で放尿機能が壊れている事(専門用語で「尿道炎」)が発覚。修理に1時間ばかりかかったせいで、閉会式に滑り込みギリギリセーフ…なんとか仮装大賞を逃さずにすみました。ついでに、記念品として120cmほどある大きくて重いクマのぬいぐるみまでプレゼントされたし…邪魔すぎ。おまけに、後から思い出したのですが…大缶の中に柄杓が入っていて、「放尿した尿を救いそれを口に運びまた放尿」という「小便小僧ターボor永久小便小僧」というネタを披露するのを忘れていました…ゴール直後で朦朧としていた頭のままで舞台に引き出されたから仕方がないのですが…悔やまれてなりません。まぁ代わりにあの大隈講堂の舞台上で放尿&粗相ができたので、良しとしましょう←良いのですか?
製作に当たっては、まず、DAKARAのCM画像から立体図をおこし、それを人が入れる大きさに拡大し、その型紙にあわせて発泡スチロールで実物大のオブジェを製作します。
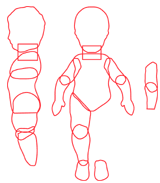  そして、ある程度仕上がったら、一度半分に割り、中に人が入れるように中をくり抜きます。この状態で、衣装合わせしようと中に入ったら、なんとなくイセエビ料理になった気分が味わえましたが…イヤハヤ。
そして、ある程度仕上がったら、一度半分に割り、中に人が入れるように中をくり抜きます。この状態で、衣装合わせしようと中に入ったら、なんとなくイセエビ料理になった気分が味わえましたが…イヤハヤ。
  ここまで作業しながらも、「関節部分だけは軽く曲がるように削った後、布&ラテックスで覆えばいいや。」と深く考えていませんでしたが、実際に関節部分の加工に入った段階で、致命的な問題が発覚。この方式ではあまりにも関節の可動範囲が狭く、着ると動けないどころか、着る事さえもままならないことが判明。オマケに関節部分を既に切削したために原型はもはや再生不可能。この時点で開催日まで残り一週間となっていたので、「今回は間に合わない…」と半分諦めましたが、どうせここまで作ったのだから、ダメ元で、安っぽい怪獣着ぐるみに使われる軟質ウレタン+布+ラテックス塗りを試してみる事に…
ここまで作業しながらも、「関節部分だけは軽く曲がるように削った後、布&ラテックスで覆えばいいや。」と深く考えていませんでしたが、実際に関節部分の加工に入った段階で、致命的な問題が発覚。この方式ではあまりにも関節の可動範囲が狭く、着ると動けないどころか、着る事さえもままならないことが判明。オマケに関節部分を既に切削したために原型はもはや再生不可能。この時点で開催日まで残り一週間となっていたので、「今回は間に合わない…」と半分諦めましたが、どうせここまで作ったのだから、ダメ元で、安っぽい怪獣着ぐるみに使われる軟質ウレタン+布+ラテックス塗りを試してみる事に…
実際にやってみたら、意外とうまい事いき、何とか再生成功しましたが、布とウレタンの接着が甘かったので、曲げるとシワが発生して見栄えがイマイチ悪くなったのは失敗。まぁ、どうにか開催日に間に合わせる事ができたので、良しとしますか。

|
 |
|